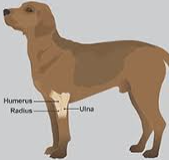関節の形成異常には先天的なものと、生後、骨の生長期に現れるものとあって、外傷や感染など後天的原因によるものと区別されます。
その主なものは、次のようなものです。
股異形成(hip dysplasia)
犬のうち特に大型犬に多発しますが、他の品種にもみられます。
新生時に一側または両側性に存在し、成長および負重に伴って進行性に悪化します。
寛骨臼の未発達にもとづく遺伝的欠陥であり、1935年G.B.Schnelleによって、犬ではじめて発見され、その後他の動物(牛、猫など)についても報告されています。
寛骨臼の凹みが浅く、大腿骨頭の嵌合がゆるく、重度のものでは寛骨臼が平坦になります。
大腿骨頭の変状は二次的で、軽症ではその大きさ、形ともに異常はないか、あるいはわずかに長軸が短縮しており、また彎曲度が減じる。
症状の進行とともに骨頭が幅広く扁平となり、大腿骨頸の骨幹となす角度が減少して、頸の軸は大腿骨長軸と同じ方向に近づく(外反股coxa valga)。
変形が重度の時はしばしば不完全脱臼subluxation、時には完全脱臼luxation or dislocationがおこります。遺伝因子はなお不明ですが、ホルモン平衡の失調、骨盤筋の異常が関係するといわれています。
症状
変状はさまざまで、臨床的には症状を現さないものもあります。
左右の股関節の間隔が正常よりも広く、後望すると骨盤部が広く、かつ扁平に見えます。歩様はぎこちなく、動揺し、走らせると後肢が兎跳びを呈するのが普通です。
膝関節が外転し、大腿骨大転子が突出し、変形が進むと上腿の筋群が萎縮します。
症例によっては、股関節部を圧迫すると、顕著な疼痛があり跛行する。異常な坐り方をします。また他の例では階段をのぼることが困難です。
しかし、一旦病機の進行が停止した後には、運動時以外では異常歩様が顕著ではなく、また疼痛も消失する例も多々認められます。
これは関節周囲組織による機能の代償によることがおおい。
予後
股関節は正常にはもどらない。
変形が著しい場合には、疼痛その他の症状が長く残存し、時には進行します。しかし、軽症では疼痛が消失することがあり、また成犬になると消失する場合もあります。
関節における微細な外傷の反復または脱臼に伴って、大腿骨頭および頸の壊死、崩壊、大股coxa magna、骨端部の変形がおこり、関節軟骨のびらん(侵食)erosionが現れる。
また関節包の弱化・伸張、滑膜層の肥厚、絨毛形成、関節液の増量、円靭帯の弱化・伸張・断裂が生じ、関節唇は肥厚し、その背側に軟膏および骨の増生をみる(変形性関節症)。
完全脱臼がある時には、寛骨臼の上に仮性関節が形成されることがあります。
変形性関節症に終わる例では、成熟後、骨端部の発育が停止すると、病機の進行もまた停止することが多い。
診断
稟告と症状によって診断可能なことがありますが、X線検査によらなければ正確な診断は下せない。
X線撮影の際には、その方向と位置が重要で、まず背位に保定し、両後肢を後方に平行に伸ばし、膝関節をわずかに内転させて、これによって、後肢に垂直位に近い肢勢をとらせて撮影します。
次に股関節を屈曲させ、軽く外転させて(frog position)撮影すると、大腿骨頭の形状を観察するのに役立つ。
治療法
本症は先天的な欠陥であるから、これを根治させる手段はなく、治療法としては、なるべく病機の進行を阻止するための対症的な方法を講ずることにとどまります。すなわち、身体の過肥を防ぎ、運動は軽度にとどめ、後軀に体重がかかるような運動は避けます。
消炎・鎮痛のためには、サルチル酸塩などの鎮痛剤あるいはステロイドホルモンを投与します。手術としては関節(切除)形成術、骨盤切開(除)術、恥骨筋切断(除)術などが行われます。